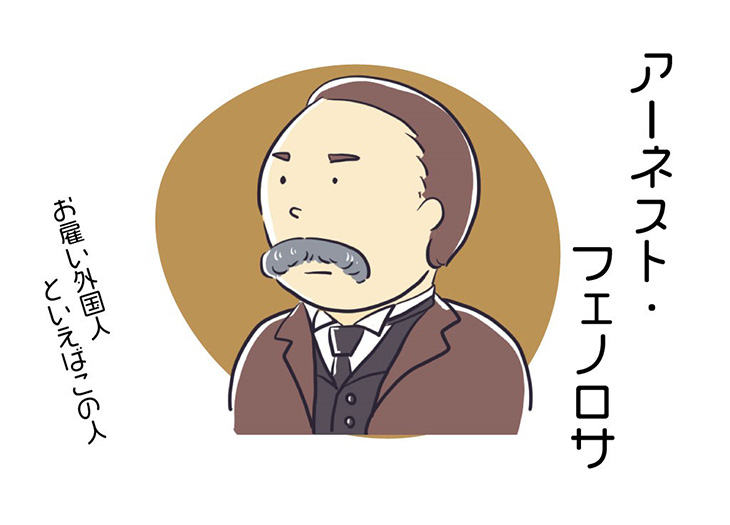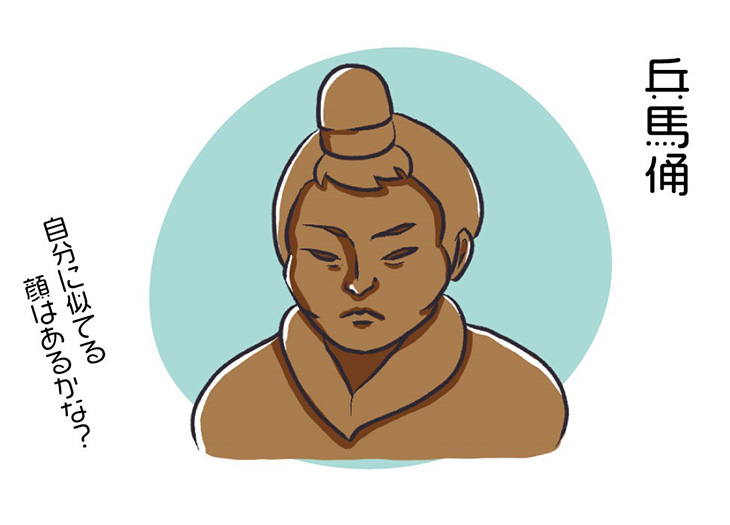江戸時代の台東区は将軍家と江戸の繁栄と安全を守るための重要な拠点だった!?

現在の台東区といえば、下町情緒あふれる庶民の街といったイメージです。
ところが今から約150年以上前の江戸時代は現在とは違い、大名屋敷や武家屋敷が多く存在した地域でした。
その理由は現在の台東区がある地域は徳川将軍家にとって重要な場所だったからです。
今回は、なぜ台東区には多くの武家屋敷が建てられていたのかについて、どこよりもわかりやすくご紹介します。
なぜ台東区には多くの武家屋敷が建てられていたのか?
台東区に多くの大名屋敷や武家屋敷が建てられた理由は、台東区が江戸城(現在の皇居)からみると北東(鬼門)の位置にあったからです。
江戸は風水の思想を取り入れて開発された都市でした。
そのため江戸城を中心にして、寺院、武家屋敷、町人街、道路が計画的に配置され、風水の「気の流れ」を整える設計が施されます。
この時、江戸城からみた鬼門(北東)の方角に守護として寛永寺(台東区上野)が建立され、鬼門封じの役割を果たしました。
上野の寛永寺はその後徳川家ゆかりの寺院になり、周辺には徳川家に近い大名や旗本・御家人の屋敷が建てられます。
このような理由で後の台東区になる地域は、幕府の戦略的な意図により武家地として開発され、武家屋敷が集中することになったのです。
次の章から台東区に建てられていた主な武家屋敷についてご紹介します。
①久保田藩の武家屋敷
1つ目は出羽国(でわのくに)を領地としていた久保田藩佐竹家の武家屋敷です。
出羽国とは現在の秋田県で、石高は20万石(実質は40万石)、大名としては外様大名です。
豊臣秀吉のもとで律義者(りちぎもの)といわれた佐竹家当主佐竹義宣(さたけよしのぶ)でしたが、関ヶ原の戦いで中立を保ったため、常陸国(ひたちのくに)から、出羽国に転封されます。
この時54万石から20万石へ大幅に石高を減らされました。
佐竹家の武家屋敷(上屋敷)があったのは台東2・3・4丁目付近です。
元々は内神田(千代田区)でしたが、1682年に焼失したため、下谷七軒町に移り明治時代まで存続しました。
関ヶ原の戦いの直後は警戒されていましたが、戦から約80年経ったこと、佐竹家が律儀で徳川家に忠誠を誓っていたこと、さらに清和源氏の流れを汲む名門であったことで幕府から信用されます。
佐竹家は外様大名でしたが、このような理由で幕府にとって重要地(台東区)に武家屋敷を建てることができたと思われます。
②対馬藩の武家屋敷
2つ目は対馬国、肥前国を領地としていた対馬藩宗家の武家屋敷です。
対馬国とは現在の長崎県対馬市のことで、肥前国とは現在の佐賀県基山町と鳥栖市の一部のことです。
対馬藩宗家は、本拠地だけでなく、飛び地が多く総石高は10万石以上(実高2万石)といわれています。
大名としては外様大名でした。
天正15年に、藩主・宗義調(そうよししげ)は、時の天下人豊臣秀吉に服属し、養子の宗義智(そう よしとし)は、小西行長らと共に、李氏朝鮮との交渉に尽力したことで有名です。
宗家は、室町時代には朝鮮王朝との通交(外交・貿易)をほぼ独占し、かなり裕福な藩でした。
宗家の武家屋敷(上屋敷)があったのは現在の台東区台東1丁目辺りです。
現在は完全に市街地になっています。
また対馬藩宗家は、江戸だけではなく、京・大坂に藩邸、蔵屋敷、博多、壱岐勝本、長崎に蔵屋敷、釜山に倭館を持っていました。
宗家が外様大名であっても幕府にとって重要地(台東区)に武家屋敷を建てることができた理由は、江戸時代に唯一李氏朝鮮との外交の窓口であったこと、鎌倉時代から続く由緒正しい家柄だったことが関係していると思われます。
③柳河藩の武家屋敷
3つ目は筑後国を領地としていた柳河藩立花家の武家屋敷です。
筑後国とは現在の福岡県南部にあたる地域のことです。
石高は約11万石でした。
大名としては外様大名です。
柳河藩は非常に領主の入れ替わりが激しい藩で、豊臣時代は立花宗茂(たちばな むねしげ)が領主でしたが、関ヶ原の戦いで西軍に加担したため一旦は改易除封(かいえきじょふう)され、領地や屋敷をすべて没収されます。
ところがその後、浪人の身となった立花宗茂はなんと敵軍の総大将であった徳川家康にその実力を評価され、2代目将軍となる徳川秀忠の御伽衆に列せられ、1万石の大名として復帰します。
その後徳川家でどんどん出世をしていき、大坂冬の陣、夏の陣で大活躍し、徳川家の勝利に貢献しました。
関ケ原の戦いから20年後の1620年に、幕府から旧領地の筑後国柳川10万9,200石を与えられ、改易されてから旧領に復帰した唯一の戦国大名となります。
立花家の武家屋敷(上屋敷)があったのは台東区東上野1丁目辺りです。
現在は完全に市街地化しています。
立花家が外様大名であっても幕府にとって重要地(台東区)に武家屋敷を建てることができた理由は、勇猛果敢であったこと、忠義者であったこと、武田信玄や上杉謙信と並ぶ器だと家康から絶賛されていたことなどです。
まとめ
今回は、なぜ台東区には多くの武家屋敷が建てられていたのかについてご紹介しました。
台東区に武家屋敷が集中していた主な理由は、江戸城の防御のためです。
特に、上野は江戸城の東北に位置し、鬼門(不吉な方角)を守る重要な役割を担っていました。
そのため徳川家康は大名や家臣の中でも特に信頼できる大名をこの地に配置します。
これらの武家屋敷は、単なる住居としてだけでなく、有事の際には江戸城に居る将軍を守るための拠点として機能しました。