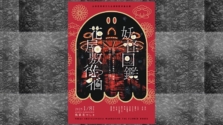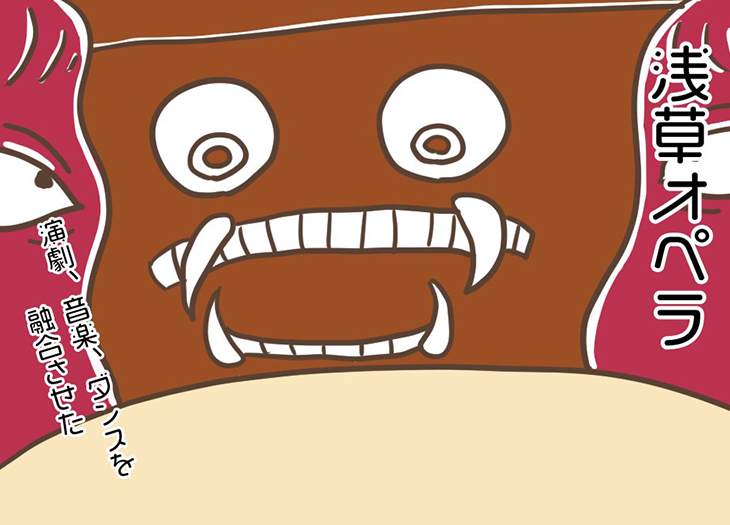招き猫のルーツは台東区!?なぜ今戸は「招き猫発祥の地」なのか?なぜ招き猫は金運・繁盛を呼ぶのか?貧しい老婆と愛猫の物語!

幸運を呼び込む縁起物として欠かせない招き猫。
その愛らしい姿は、多くの店舗や家庭で「福」と「富」を招き続けています。
では、この偉大な開運のシンボルは、どこで誕生したのでしょうか。
実は、意外にも台東区の「今戸(いまど)」といわれています。
その背後には、人生のどん底にあった老婆の運命を、彼女の愛する猫が変えた感動的な物語がありました。
今回は、なぜ今戸は「招き猫発祥の地」なのか、貧しい老婆と愛猫の物語について、どこよりもわかりやすくご紹介します。
招き猫発祥の伝説・貧しい老婆と愛猫の物語!
招き猫発祥の伝説は、「武江年表(ぶこうねんぴょう)」、「藤岡屋日記」によると、次のように伝えられています。
江戸幕府の終焉が近づく1852年(嘉永5年)。
浅草・花川戸(現在の台東区内)の片隅に、つつましく商いを営む一人の老婆が住んでいました。
一人暮らしで身寄りのない彼女の唯一の家族が一匹の白ぶち猫です。
彼女は猫を心から可愛がり、どんなに生活が苦しくても、猫を決して手放そうとはしませんでした。
ところが生活は日に日に困窮し、ついに彼女は生活を維持できなくなってしまいます。
愛猫に満足な食事を与えることさえ難しくなり、苦渋の決断を迫られます。
「このままでは、お前まで飢えさせてしまう」
愛する猫の幸せを願い、ついに手放すことを決意した老婆は、悲しみに暮れながら猫に別れを告げ、外へ放してしまいました。
その夜、悲しみに打ちひしがれて眠りについた老婆の夢の中に、放したはずの愛猫が現れます。
「あなたは、私の姿を焼き物にして祀れば、必ず福が訪れるでしょう」
愛猫は、彼女にそう告げ、姿を消しました。
夢から覚めた老婆は、愛猫の言葉を信じました。
彼女は、今戸焼の技術を持つ近隣の職人、または自らが土をこねて、愛猫の姿を模した焼き物を作ります。
これが、現在の招き猫の原型になったと言われています。
彼女はさらに、その焼き物を町の入り口や道端に置き、「福を招く猫」として売り出しました。
すると、どうでしょう。
その猫の焼き物が評判となり、飛ぶように売れ始めたのです。
「あの猫を買ってから商売が繁盛した」
「病気が治った」
「思わぬ幸運に恵まれた」
といった噂がたちまち江戸中に広がり、老婆の焼き物は大人気となりました。
老婆は、この猫の焼き物のおかげで貧しさから抜け出し、晩年を豊かに過ごすことができました。
※武江年表とは江戸の庶民が実際にどのように暮らしていたかを生き生きと知ることができる資料のことです。
藤岡屋日記とは一人の古本屋の主が、市井(町中)のゴシップや噂、事件、流行といった、より生々しい庶民の生活情報を集めた「私的な日録」のことです。
なぜ今戸焼が招き猫を生み出したのか?
今戸焼とは、現在の台東区の今戸や橋場周辺で焼かれていた陶磁器のことです。
今戸焼の起源は戦国時代の1590年(天正18年)、豊臣秀吉による小田原城攻めによって北条氏に従って滅亡した下総国(しもうさのくに)千葉氏の家臣数人が今戸周辺に土着して、土器類を作り始めたのが起源といわれています。
下総国とは、現在の千葉県北部と茨城県南西部にあたる地域のことです。
「武江年表」、「藤岡屋日記」によると、元々最初は老婆が白ぶち猫の焼き物を浅草神社の鳥居の辺りで一人で売っていたといわれています。
その後、猫の焼き物を飾るとご利益が得られると評判になり、浅草寺の二天門辺りの露天商の屋台で、白ぶち猫の焼き物が売られるようになりました。
ここから猫の焼き物づくりが、今戸周辺で広がっていったといわれています。
この白ぶち猫の焼き物は、当時「〇〆猫(まるしめのねこ)」と呼ばれていました。
〇〆猫(まるしめのねこ)」とは何か?
〇〆猫とは、現在の招き猫のルーツ(元祖)の一つとされる猫の焼き物のことです。
最大の特徴は、背中や腰のあたりに付けられた「〇」の中に「〆」の文字が描かれていることです。
屋台では「〇〆(まるしめ)」の染め抜きの暖簾が掲げられていました。
「〇〆」とは、「お金や福を丸ごと勢〆(せしめ)る」という意味です。
一般的な招き猫と同じように片方の前足を上げて福を招くポーズをしていますが、体つきや顔つきは素朴で愛嬌があり、現在の招き猫とは少し異なる独特の雰囲気を持っています。
〇〆猫は、江戸っ子の縁起担ぎの心から生まれた、「福やお金をひとりじめにする」願いを込めた、招き猫の原型とも言える土人形でした。
ここから数年間、〇〆猫ブームが続くことになります。
歌川広重の錦絵「浄るり町繁花の図」にも描かれた「〇〆猫」の姿
「浄るり町繁花の図」の発表が1853年(嘉永6年)なので、老婆が白ぶち猫の焼き物を売り出した翌年には、他の露天商も〇〆猫として売り出していたことになります。
この錦絵の最大のトピックは、招き猫の具体的な販売風景を描いた、現存する最古級の資料であることです。
錦絵には、浅草寺の境内近くで露天商が物を売っている様子が描かれています。
その露天商が売っている土人形の中に、今戸焼の「〇〆猫」の姿をはっきりと見ることができます。
この絵のタイトルにある「浄るり町」は、浅草寺周辺にあった芝居小屋などが集まる賑やかな地域のことです。
寺社境内の露店、人々が行き交う様子、季節の縁起物(羽子板など)が売られる風景など、当時の庶民の生活や文化が詳細に描かれています。
広重らしい、賑やかで生き生きとした様子が特徴の錦絵です。
まとめ
今回は、なぜ今戸は「招き猫発祥の地」なのか、貧しい老婆と愛猫の物語についてご紹介しました。
これまで縁起物として知られていた招き猫の背後には、台東区今戸という場所で生まれた、貧しい老婆と愛猫の深い愛と感謝の物語がありました。
実は台東区は、江戸時代から庶民の活気と義理人情が息づく特別な場所です。
招き猫の伝説がこの地で生まれたのは、ただの偶然ではありません。
それは困っている人や動物への温かい眼差しが当たり前にある、この土地の「優しさ」の表れとも言えるでしょう。
さあ、あなたも一度台東区今戸へ足を運び、ぜひ招き猫たちに会いに行ってみませんか。