「生ごみ」をごみとして処理しない!?台東区が推進する都内で初めての取り組みとは
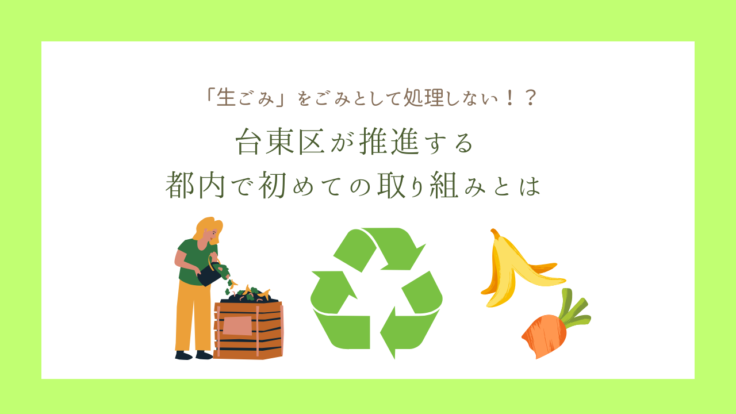
みなさんは普段生活するなかで、生ごみをどの程度排出しているかご存知でしょうか。
「令和元年度台東区廃棄物排出実態調査」によると、台東区で排出される燃やすごみのうち、約1/3を生ごみが占めているという結果となっています。
区は、生ごみの排出量を減らすべく、生ごみを堆肥化する「コンポスト」の推奨に励んできました。
2023年には、都内で初めて事業者と「循環型ライフスタイルへの転換に向けた協定」を締結し、生ごみ減量の目標達成に向けた道を本格的に歩み始めたのです。
どんなものが堆肥にできる?
堆肥にできる生ごみとして代表的なものは次のものがあります。
・野菜や果物の皮
・使用済みの油
・白いご飯
・パン粉
・茶殻 など
野菜や果物の可食部分やタンパク質以外の味付けされていない残飯であれば、堆肥にすることができます。
台東区では、上記のようなコンポストについて学べる講座やイベントが定期的に開催されています。
「コンポストに挑戦したかったけどきっかけがなかった」「環境のために何かエコなことをしたい」方は、各種イベントへ参加されてみてはいかがでしょうか。
2025年5月31日開催!イベント「循環生活コトハジメ」
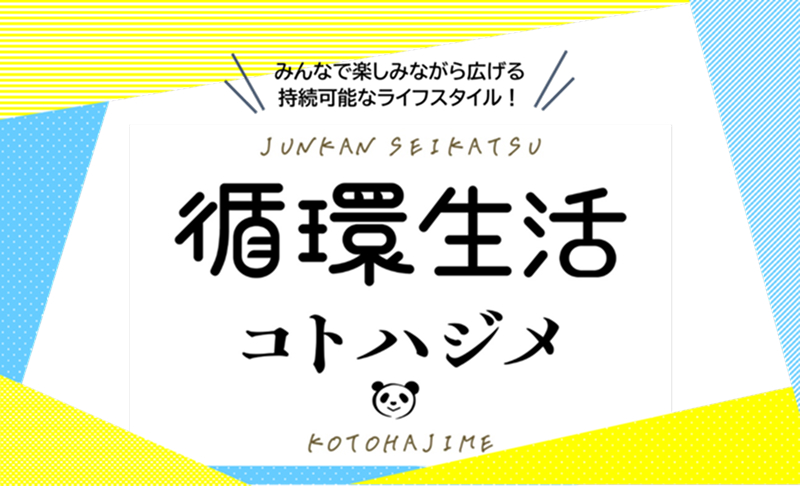
「コンポストでの生ごみ循環」や「循環型のライフスタイル」をテーマとして、以下のような催しが予定されています。
・台東区内にある企業がマルシェを開催
・キッズフリーマーケット
子供自身が自ら考えて行うフリーマーケット
・コンポストに関する講座やワークショップ
「初めてのLFCコンポスト講座」
「ハーブティ作り講座」など
お子様の学習の一環として参加するのもおすすめです。
また、同時に資源の回収も行われる予定です。
【回収対象の資源】
・歯ブラシ
・紙パック、牛乳パック
・使用済み食用油(各家庭1L以下)
・不要な食品(賞味期限が1ヶ月以上残っている常温食品)
このうち、歯ブラシや紙パック、牛乳パックを所定数持参すると、日用品に交換してもらえるキャンペーンもありますので、この機会にぜひ持ち込んでみてはいかがでしょうか。
開催日時:2025年5月31日(土) 10時〜16時
開催場所:御徒町南口駅前広場(おかちまちパンダ広場)
堆肥de!ガーデニング講座
コンポストでできた堆肥を実際に使って、野菜を育てるために必要な知識を実践的に学ぶことができる講座です。
過去に開催された回では、実際に生ごみから作られた堆肥を使用して、スナップエンドウの種を植え、植え方や水やりの仕方、手入れの方法などが紹介されました。
次回開催日は未定のようですので、参加してみたい方は台東区のHPをこまめに確認するようにしましょう。
定期開催「はじめてのコンポスト講座」
こちらの講座では、区と協定を結んでいる事業者(ローカルフードサイクリング株式会社)がアドバイザーとなり、コンポストにまつわる知識を教えてくれます。
生ごみを減らして循環型社会を形成する第一歩として、とっつきやすいテーマを取り扱っているため、コンポストに挑戦してみたい方は参加してみてはいかがでしょうか。
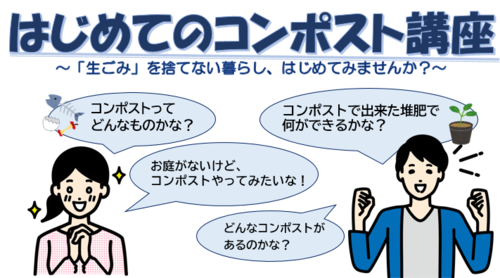
堆肥の回収ができるコンポスト容器
これまでは、生ごみから堆肥を作ったとしてもその堆肥を家庭でうまく活用できなかったことが、コンポストを普及させるうえでの障壁となっていました。
そこで、区では事業者と協力して、堆肥の回収ができるコンポスト容器の周知に取り組んでいます。

生ごみの排出量を減らすためにできることは?
生ごみの排出量を減らすためにわたしたちができること。
それは、食品のロスを減らすことと生ごみの水分量を減らすことです。
生ごみの組成の約8割は水分であり、水分が含まれていればいるほど焼却する際に消費する燃料が増えて、環境への影響が大きくなります。
そのため、生ごみを出す際にはしっかりと「水切り」することを意識するようにしましょう。
三角コーナーなどで水を切って乾かしてから捨てることのほかに、生ごみを「ひとしぼり」するなど、とにかく脱水してから捨てることが大切です!
まとめ
台東区は、23区のなかでも特に食品ロス削減と生ごみの減量に力を入れている区のひとつです。
今回ご紹介したイベントや取り組み以外にも、区では様々な取り組みを実施しており、生ごみ減量への熱意が窺えます。
・食品ロス削減を啓発する日「たいとう食ハピDay」を毎月30日に設定し、HPとSNSで情報を配信
・たいとう食ハピすごろくの配布
・賞味期限間近などの理由で一般流通できなくなったフードロス商品をお得に商品購入できる販売機「fuubo」を区役所内に設置
・食品ロス削減レシピの考案
・食品ロス削減の啓発ポスター配布 など
区のHPでは、食品ロスや生ごみ減量についての豆知識の発信が定期的にされていますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。
わたしも家庭でできることを少しずつ取り組み、持続可能な社会を目指す第一歩を踏み出したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございました!













